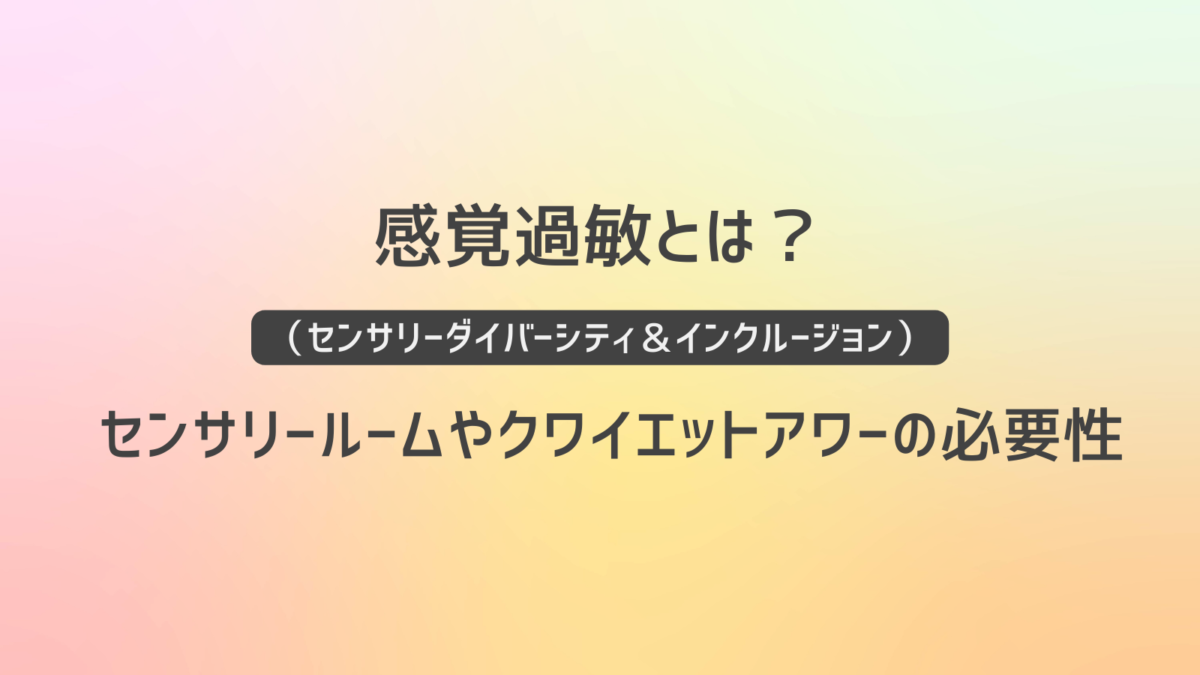
感覚過敏とは?
感覚過敏とは、視覚、聴覚、嗅覚、味覚、触覚などの諸感覚が過敏で、日常生活に困難さがある状態をいいます。感覚過敏は病名ではなく症状です。感覚過敏は発達障害の人に多く見られる症状ですが、うつ病、認知症、脳卒中、てんかん、交通事故による脳へダメージ、HSPなどでも見られる症状です。
感覚過敏の特徴
以下のような症状がみられます。複数の感覚が過敏な方もいらっしゃれば、1つの感覚が過敏な方もいらっしゃいます。まだ、人によって苦手なものや過敏の反応も違います。ゆえに、画一的な対策や工夫が難しいという課題があります。
視覚過敏
- スマホやパソコンの画面の光が目に刺さる感じで痛い。
- スマホの画面を一番暗くしても眩しい。
- 太陽の光で頭が痛くなる。
- 白い紙や画面がまぶしくてつらい。
- 人が多いところに行くと具合が悪くなる(視覚情報の多さに疲れる)
聴覚過敏
- 蛍光灯や時計の秒針の音が絶えず聞こえてつらい
- 目の前の人の声と周りの声の音量が同じくらいに聞こえ、会話が聞き取りにくい
- 大きな音に恐怖を感じる。
- 子どもの声や赤ちゃんの泣き声が苦手。頭が殴られたように痛く感じる
- 騒がしい場所にいると体調が悪くなってしまう
嗅覚過敏
- 電車内での体臭や香水、化粧品、衣類などのニオイで気分が悪くなる
- 食べ物や給食のニオイで頭痛や吐き気がする
- トイレの芳香剤の香りに苦痛を感じる
- 周囲の人が着ている服から香る柔軟剤で気分が悪くなる
- 街中の車の排気ガスや飲食店からするニオイなど様々なニオイが混ざり合っていて外にいるのが苦痛
味覚過敏
- 味に敏感で食べられるものが極端に少ない
- 味や調味料の変化に敏感で、少し普段と違うと食べ物を受け付けなくなる場合がある
- 食感にも苦手なものが多い
触覚過敏
- 人に触れられることが苦手で、側に寄られるだけでも逃げたくなる
- 服のタグ、縫い目などに痛みや不快感を感じ、快適に着られる衣服が少ない
- 口周りが敏感な場合、マスクの着用が難しい(痛みや不快感を感じる)
- 重さ、窮屈さ、素材の感触などにより、服や靴下を身に付けるのが苦痛
- 雨や風が当たると不快感や痛みがある
感覚特性や感覚の多様性に配慮した社会の必要性
上記のような感覚の過敏さがあると日常生活は困難なことの連続です。解決方法や緩和方法もない現状で、感覚過敏のな方々の生活を支える方法は多くはないのが現状です。
しかし、空間や時間などを五感に配慮したものにする工夫は今すぐにでもできることです。たとえば
- お店や施設の照明やBGMを落とした時間帯を設定し、感覚過敏のある人が安心して来店・滞在できるようにする(クワイエットアワー)
- 光や音に配慮した空間を作り、ライブやスポーツ観戦を楽しめる機会を提供する(センサリールーム)
- 施設内に落ち着ける空間を用意し、安心して滞在できるようにする(センサリールーム、カームダウンスペース)
- 街や施設の五感情報(音がうるさい場所、ニオイが出ている場所など)をマップ化することで、苦手な場所を回避し落ち着いて行動することができる(センサリーマップ)
などです。
感覚は目に見えず、他人の感覚を体験することができないため、これまで感覚の過敏さで困っていることがなかなか認知されない社会でした。しかし、今、世界では少しずつ感覚に配慮した取り組みが増えてきています。
クワイエットアワーとは?

Quiet Hour(クワイエットアワー)とは、お店のBGMや照明を落として、感覚過敏の方が落ち着いて買い物や館内滞在できる時間帯やキャンペーンデーのことをいいます。
欧米諸国の大手スーパーマーケットでは、積極的にクワイエットアワーを導入されています。クワイエットアワー導入時間の売上が他の時間帯より10%アップしたというレポートもあるようです。また、照明やBGMなどを落とすことによって光熱費の削減にもつながります。
センサリールームとは?
センサリールームは、音や光、ニオイなどの五感の刺激を少なくし、聴覚・視覚など感覚過敏の症状がある人やその家族が安心して過ごせる空間・部屋のことです。
同じ「センサリールーム」という呼び名でも実際は3種類あります。
感覚刺激を少なくしスポーツ観戦やライブ観戦などを楽しめるスペース

サッカーやバスケットなどのスポーツ施設やライブ会場などで、周囲の音や光などを気にせず観戦や鑑賞を楽しめるスペースです。(写真:東京ヴェルディにて。撮影:感覚過敏研究所)
感覚・感情を落ち着かせるスヌーズレンを利用したセラピールーム

スヌーズレンは、知的障害や精神疾患がある方が感覚刺激を自由に楽しめる空間やプレイセラビーとして福祉施設や医療施設に導入されるだけでなく、海外では一般家庭に、子どもたちの感性や感覚を育むアプローチとして取り入れられています。
公共施設や商業施設において感覚刺激を回避できるスペース

感覚刺激に疲れた時に、気持ちや体調を整えるために一時的に避難したり休憩するためのスペースです。「カームダウン・クールダウンスーペース」と呼ばれています。
センサリーマップとは?/ Sensory Map

Sensory Map (センサリーマップ)とは、光や音、ニオイなどの五感情報をマップに表示させたもので、感覚過敏や感覚特性がある人は、その感覚情報を見て、その場所を回避したり、対策を考えてその場所に行くことができます。
また、静かな場所、休憩場所、センサリールームやカームダウンスペースなどのマップ情報があると、感覚特性がある方々も安心して外出できます。
センサリーD&I(ダイバーシティ&インクルージョン)な社会を目指したい
センサリールームやクワイエットアワーは感覚刺激に強い反応をする方々にとって安心できる空間や時間です。日本ではまだ浸透していない取り組みです。感覚過敏研究所SDI推進室としても、センサリールームの社会実装に力を注ぎたいと考えております。ご賛同くださる方、ともに社会実装に取り組んでくださる企業様・パートナー様を広く募集しております。
感覚過敏研究所SDI推進室ができること
- センサリールームやクワイエットアワー導入のご相談やコンサルティング
- センサリールームやクワイエットアワーの導入や運営方法のご相談やサポート
- センサリーマップの作成と実地調査
- ソーシャルグッドな取り組みのプロモーションや企業ブランディング
- 感覚過敏の当事者やご家族への情報提供
- センサリールームやクワイエットアワーの導入や運営のためのスポンサーの獲得
- センサリーフレンドリーな商品開発、テストモニター、官能評価
- センサリーフレンドリーな空間・時間・商品・サービスの認定